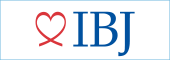京都市左京区で婚活・お見合いするなら結婚相談所
縁結び 幸せリボン
〒606-8203 京都府京都市左京区田中関田町26-10 Mビル3F
美容室グレースヒロコ
お気軽にお問合せください
営業時間 | 10:00〜18:00 (不定休) |
|---|
「結納」当日ってなにをするの?結納のマナーや注意点と費用について解説!

2025.04.17
近年では「正式結納」を行うカップルは少なく、「略式結納」もしくは「顔合わせ食事会」の形式を選ぶ方がほとんどです。
略式結納は、料亭やレストランなどに両家が集まって結納品を交わします。
仲人が立ち合う場合もありますが、本人たちと親だけで行うことがほとんどです。両家が一堂に会するという点が略式結納の特徴です。
「略式結納」は、「正式結納」とは異なり堅苦しいものではありませんが守るべきルールはあります。
ここでは、「略式結納」当日の流れとマナーや注意点、費用についてご紹介します。

当日の流れ
略式結納の当日の流れについてご紹介します。
【結納当日の流れ】
結納の儀式は20分程度で終了し、その後は記念撮影や食事会を行い両家の親睦を深めます。
進行役は本人同士や両家の父親がする場合と仲人を立てる場合があります。
ここでは、男性側の父親が進行役をする場合についてご紹介します。
❶ 結納品を飾り、両家が着席
結納を行う前に、まずは結納品を飾ります。
和室の場合は床の間やその前に飾り、洋室の場合はテーブルの上に飾ります。
地域の習慣によって異なりますが、向かって右側に男性側、向かって左側に女性側の結納品を飾るのが一般的です。
結納品を飾り終えたら男性側が先に入室し、次いで女性側が入室します。
参加者全員がそろったところで着席し結納の儀式を始めます。
男性側は上座、女性側は下座に座りますが、結納では本人たちが上座(結納品に近い場所)ということを覚えておきましょう。
並びは上座から本人→父→母の順番です。
儀式が終わるまでは、挨拶や口上以外はあまり口にしないように注意しましょう。
↓
❷ 初めの挨拶(男性側の父親から)
初めのあいさつは、進行役を務める男性側の父が行いますが不在の場合は母や男性本人がその役目を引き受けます。
(口上例)
「このたび、お嬢さまと私どもの息子とご縁がありましたこと大変嬉しく思っております。
本日はお日柄もよろしく結納を納めさせていただきます。」
↓
❸ 結納品を納める(男性側→女性側)
男性の母が『結納品と家族書をのせた台』をお盆ごと女性本人の前へ運んで一礼します。
母が席へ戻ったら、男性の父が口上を述べて深く一礼します。
(男性の父の口上例)
「ご縁組の印として結納の品々を納めさせていただきます。目録をお改めの上、幾久しくお納めください。」
↓
❹ 女性側からの受書の渡し
受け取った結納品の中から、女性本人が『目録』を手に取って中を改め、さらに父→母へと渡し全員で目を通します。
それから女性本人が口上を述べて一同深く礼をします。
続いて女性の母が受け取った結納品を飾り台へ運び、受けとりましたという『受書』を男性に渡し、「受書でございます。幾久しくお納めください」と伝達します。
男性は受書を確認し、続いて父母も確認します。『受書』を男性本人へ渡して一礼します。
(女性本人の口上例)
「ありがとうございます。幾久しくお受けいたします。」
↓
❺ 結納返しを納める(女性側→男性側)*関東式
女性側の親が『男性側へ贈る結納品と家族書をのせた台』を男性本人の前へ運んで一礼します。
席に戻ったら、女性側の父が口上を述べて深く一礼します。
(女性側の父の口上例)
「先程は結構な結納の品を頂きましてありがとうございました。そちらは〇〇(または私ども□□家)からの心ばかりの御礼の品でございます。幾久しくお納めください。」
↓
❻ 男性側からの受書の渡し*関東式
受け取った結納品の中から、男性本人が『目録』を手に取って中を改め、さらに父→母へと渡し、全員で目を通します。
それから男性本人が口上を述べて一同深く礼をします。続いて男性の親が受け取った結納品を飾り台へ運び、『受書』を男性本人へ渡して一礼します。
(男性本人の口上例)
「ありがとうございます。幾久しくお受けいたします。」
↓
❼ 結婚記念品のお披露目
婚約指輪などの『婚約記念品』を準備している場合はお互いに交換します。
すでに婚約記念品を交換済みの場合は、この場でお互いの両親にお披露目しましょう。
進め方に決まった手順や口上があるわけではありませんが、結納式の流れに沿って厳かなに披露目してみてはいかがでしょうか。
(女性本人の口上例)
「このたびは婚約記念品として、□□さんから婚約指輪を頂きました。すでに指に着けていますが、改めて皆さんにお披露目させてください。」
(男性本人の口上例)
「このたびは婚約記念品として、〇〇さんから腕時計を頂きました。これから始まる結婚生活とともに、長く大切に使っていきたいと思います。」
↓
❽ 結びの挨拶(男性側の父親から)
締めの口上を述べる。
男性側の父が口上を述べた後に女性側の父が返礼する形で締める。
初めのあいさつと同様に進行役を務める男性側の父が行います。
続いて女性側の父(不在の場合は母)が返礼の口上を述べ、全員で「今後ともよろしくお願いします」と丁寧にあいさつをしてお開きを迎えます。
「無事に結納を納めることができました」という結びの言葉で結納式は終了です。
(男性側の父親の口上例)
「本日は誠にありがとうございました。おかげさまで無事に結納を納めることができました。今後とも末永くよろしくお願いいたします。」
(女性側の父親の口上例)
「こちらこそありがとうございました。今後とも末永くよろしくお願いいたします。」
↓
❾ 記念撮影
全員の集合写真を撮る。
↓
➓ 祝宴
結納後はお祝い膳を囲み、両家の親睦を深めます。
無事に結納が終わり、両家の親戚付き合いがこれから始まることを祝って和やかな歓談のひとときを楽しみましょう。
時間の目安は2~3時間です。
料亭やホテルなどの『結納プラン』を利用する場合はそのまま同じ会場で、自宅で結納をした場合は仕出しを頼んだり、料亭などに場所を移して行うことが多いようです。

結納のマナー
略式結納を執り行う際、注意すべき点を4つご紹介します。
略式といえども婚約を調える伝統的な儀式になるのでマナーを理解し臨むようにしましょう。
❶ 略式結納における服装マナー
フォーマルでもセミフォーマルでも問題ありませんが、出席者の服装の「格」は揃えます。
女性が振袖なら男性はダークスーツを着用しましょう。
母親は色無地紋付、付け下げ、父親はダークスーツで臨みます。
最近はセミフォーマルが一般的になっています。その場合、女性はきちんとした印象のワンピースがおすすめです。明るい華やかな雰囲気の服装が良いでしょう。
和室会場なら立ったり座ったりすることを考え、あまりタイト過ぎないシルエットで、丈は膝が隠れる程度のスカート丈にします。セミフォーマルの場合、母親もフォーマルスーツ・ワンピースなどでも問題ないとされています。
❷ 結納品は省略してもOK
結納金や婚約記念品を交換するのみで結納が行われるケースも増えており、結納品は省略しても問題ありません。
結納品の場合、合計品目は『割り切れない奇数』になるようにするのがマナーとされています。
【略式結納における席順】
席順については、床の間に向かって左側に男性家族、右側に女性家族が座ります(※地域によっては逆の場合もあります)。
一般的な席順のマナー同様、入口から遠いところが上座で、床の間がある場合、床の間の前が最上位の席になります。
入口から遠い上座側に、男性本人→父親→母親の順番で着席します。
女性側は男性家族に向き合う並びで、女性本人→父親→母親の順に着席するのがマナーになります。
❸ 使ってはいけない忌み言葉
結納はおめでたい席になるので、縁起が悪いとされる以下の「忌み言葉(いみことば)」は使わないようにしてください。
「破談や別れをイメージさせるネガティブな言葉は使わない」と覚えておき、会話中うっかり使用しないよう意識しましょう。
・別れる(分かれる)
・切れる
・離れる
・壊れる
・「重ね重ね」「たびたび」「くれぐれも」といった重ね言葉
❹ 結納品は風呂敷に包んで持参
結納品は、風呂敷に包んで持参するのがマナーです。
紙袋・ビニール袋で代用してはいけません。
結納品を包む際、結ばず掛けるようにしましょう。
大きい結納品の場合は一箇所だけ結ぶ方法も許されていますが結び目を持たないように注意してください。
一般的に別れを連想させるものとして結び目があり、作らないほうが良いとされています。
結納品を持ち帰る際、逆に結んだ縁がほどけないようしっかり風呂敷を結びます。

結納の注意点
ここでは結納の注意点を5つご紹介します。
❶ 手土産はいる?
手土産を用意する必要はないですがもらうと嬉しいものです。
ただし一方だけが用意し、もう一方が手ぶらという状況は気まずいので、ふたりの間で打ち合わせをしておくことが大切です。
また地域によっては風習として手土産を持参するのが当然ということもあるので親にもよく確認しておきましょう。
❷ 地域や家のしきたり
地域や家によってしきたりが異なるのは仕方がないことです。
お互いに自分たちのやり方を主張し合うのではなく、それぞれの結納の形式を確認しどちらに合わせるか調整が必要です。
特に関西式では男性側が女性側に「贈る」という形を取るため、男性側の意向が尊重されがちですが、できれば「こうしたい」という思いが強い側に合わせた方が丸く収まります。
❸ 親以外の参加
親以外の家族の参加は基本的には当事者である両家の親とふたりのみで行うのが結納です。
とはいえ地域のしきたりで家族全員が出席するのが普通だったり、儀式の後の会食を「家族紹介」の場にしたい場合もあります。
そんなときは両家で考え方を擦り合わせ、相談しながら進めるといいでしょう。
❹ 遠方の場合
両家の地元が離れているときは特にどこで行うかも重要なポイントになります。
どちらかもしくは双方が遠方へ出向く場合は旅行の手配なども必要になってきます。
❺ 各サービスの活用
自分たちで行うのか「結納プラン」や「結納パック」などを利用するのかによって、準備の手間もずいぶん変わるので早めに決めておきましょう。

準備するもの
ここでは結納までに準備するものを6つご紹介します。
❶ 結納品
婚約の証しとして取り交わす品々のことです。
一般的には9品目が正式とされますが、7品目や5品目、3品目などのケースもあります。いずれも割り切れない奇数の品目であることが決まりになっています。
結納品は大きく関東式と関西式に分けられ、関東式では両家が結納品を用意するのに対し、関西式では男性側だけが用意するのが一般的です。
❷ 結納金
結納の際に、男性側から女性側へ贈られる結婚の準備金のことです。男性が婿入りする場合は、女性側から男性側に贈られます。
結納金は結納品の1品目として、結納の際に相手方に手渡します。かなりの高額になりますが、基本的には現金を包みます。結納飾りの中に立派な金包かのしが掛かった桐の箱があるので、それに現金を入れます。
❸ 結納返し
結納品に対するお返しで、品物とお金を贈るのが本来の形です。
関東では結納金の半額を返す「半返し」、関西では1割程度の金額を返すのが一般的とされています。しかし、最近は結納返しを簡略化もしくは省略することもあり、お金ではなく婚約記念品を結納返しとして贈ることも多くなっています。
品物の場合は、本人の希望を聞いて選んでもらいましょう。腕時計やスーツなど記念に残るものがおすすめです。
❹ 婚約記念品
婚約の記念に贈る品のことで、男性から女性に贈るのは婚約指輪が一般的です。女性から男性への婚約記念品は、腕時計やスーツが人気です。
関西式の結納では、婚約記念品(婚約指輪)を結納品として贈りますが、関東式では結納品に含みません。
結納の席での婚約記念品のお披露目は多くの人が実施しています。最近は、男性への婚約記念品を結納返しとして贈る場合もあります。
❺ 家族書・親族書
「家族書・親族書」は結納をする場合に必ず用意しなくてはならないものではありません。例えば、地元が同じでお互いの家族をよく知っている場合など、「家族書・親族書」の用意を省略することもあるようです。
結納の儀式の中で「家族書・親族書」を用意するかどうかは、ふたりの親の意見を聞いて決めましょう。
❻「結納の挨拶・口上」「目録」「受書」
結納当日に向けて準備しておきましょう。
両家が足並みを揃えて結婚準備を進めるためにも、みんなの都合を確認し早めに準備することが大切です。

結納にかかる費用
結納でかかる費用には、結納金、結納品、結納返し、結納式の費用(会場費や食事代など)などがあります。
ここでは結納にかかる費用についてご紹介します。
【結納品】
結納品は男性側から女性側へ贈ります。
男性側から女性側へのみ納める場合は、基本的に男性側のみの負担になり、双方が結納品を用意して取り交わす場合は両家それぞれが納める結納品の費用を負担します。
結納品の品目数は9品目が正式といわれますが、最近では簡略化することも多く、7品目や5品目、3品目の場合もあります。
品目数に応じて1〜20万円程度になり、結納品費用の平均額は14.9万円です。
また、男性から女性に婚約指輪を贈る場合は、結納品に含めるのが一般的です。その際は、指輪台を用意して結納品とともに贈るほか、目録に記す場合もあります。なお、婚約指輪の平均額は35.0万円です。
【結納金】
結納金は、結婚の支度金として男性から女性へと贈るものなので男性側が負担します。
ただし、婿養子などの場合は女性側が男性側へ結納金を納めることになるので女性側が負担します。
50万円や100万円などキリのいい数字で贈ることが多く、50万〜150万円で贈る人が多いようです。
【結納返し】
結納返しは、女性側が男性側へお金や品物を納めるものなので女性側が負担します。
頂いた結納品や結納金に対し女性から男性に結納返し品や現金、品物(婚約記念品)などでお返しをするのが結納返しです。
結納返しは地域によって対応が異なります。
現金の場合は10〜60万円、品物の場合は5〜30万円程度が相場になります。
【関東】では結納返し品は結納品とほぼ同じ品数で同じ品物を返します。
現金のお返しの目安は頂いた結納金の半額程度で、30万円や50万円などキリのいい数字にします。
半額を返すため、半返しと呼ばれます。
【関西】では結納返しはしないか、後日(荷送りの時など)に相手の家族のお土産として1割程度の金額を返すのが一般的です。
最近では当日にお返しすることも多くなっています。
また、品物の結納返しでは、腕時計やスーツ、かばん、靴など身の回りのものなどを贈るのが一般的です。
結納は地域によって異なる常識やルールがあり両家にはそれぞれ考え方もあります。
まずはふたりでどのようにしたいのか、意見をまとめて両家の親にも相談し準備を進めましょう。
【結納式の費用】
結納は結納式と食事会がセットで行われるのが一般的です。
結納品のやり取りなどが行われる儀式が結納式で、その後、両家の親睦を兼ねて食事を楽しみます。
近年では料亭やホテルで行われることが多いようです。
結納式と食事会の費用総額の平均額は18.4万円です。数万円〜20万円程度が相場のようです。
【結納式の費用分担】
分担が難しいのが、食事代や会場費などの結納式の費用です。
昔は男性側が女性側の家を訪ね女性側の家で結納の儀式と食事をするのが一般的でした。
もともとは、「結納を行う場所」と「食事」は女性側が用意し男性側は食事代の一部を負担していました。
最近では結納を女性側の家だけでなくホテルや料亭などで行うことも増えてきています。
結納式と食事代の費用の分担方法には大きく分けて次の2つがあります。
・女性側が負担する(もともとのやり方にしたがって、女性側が費用を負担する。)
・男性側と女性側で半分ずつ負担する
また、結納をする場所によってはどちらか一方が遠方から来ることになり会場費や食事代以外にも「交通費」や「宿泊費」がかかる場合もあります。
その場合は、交通費や宿泊費も含めて分担し費用負担が両家で同じぐらいになるように調整する方法もあります。
費用の分担方法にはっきりとした決まりはないので、両家の状況や希望をふまえてお金の問題はあいまいにしておくとしこりが残る可能性もあるため双方でしっかり話し合って決めておきましょう。
最近では、結納金や結納品、結納での食事代などを親ではなく結婚する二人自身が負担するケースも増えているようです。
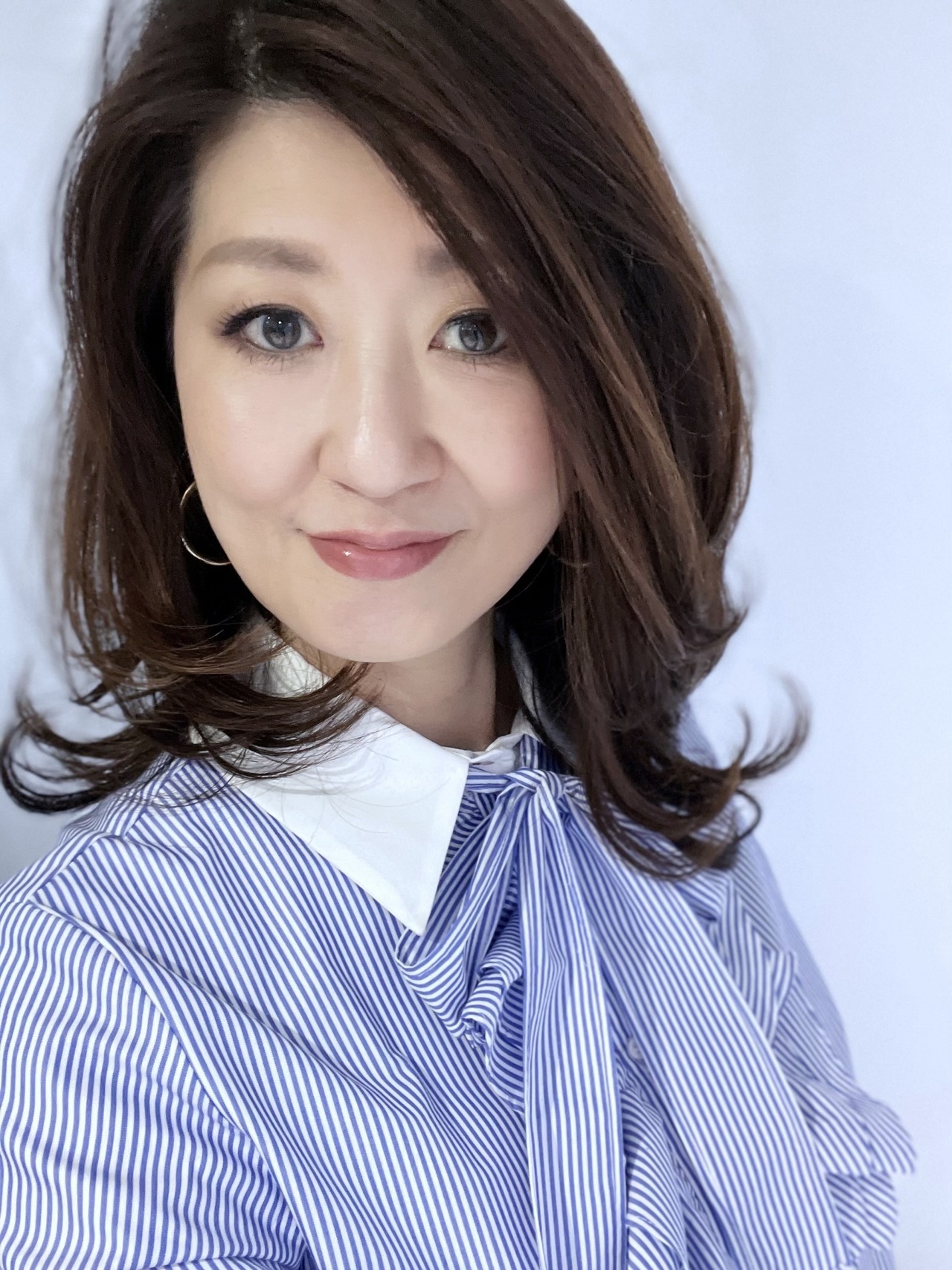
代表カウンセラーの山内です。
一緒に婚活始めませんか!
略式結納とは言え結納は決まりごとの多い儀式です。
晴れの日を滞りなく進めるために流れやマナー注意点を意識して臨みましょう。
ホテルなどで用意されている結納プランの利用もおすすめです。
この記事が、あなたの婚活にとって少しでもお役に立てれば幸いです。
京都で出会いをお探しなら、京都市左京区の結婚相談所「縁結び 幸せリボン」まで是非ご連絡ください。無料相談では、縁結び 幸せリボンのサービスを十分にご理解いただくことでご自身の婚活のイメージを深めていただけると思います。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方は、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。